はじめに
建設業を営む中で、
✅ 「元々取得している業種に加えて、別の業種も追加したい」
✅ 「将来の事業拡大に備えて、複数業種の許可を取りたい」
というケースはよくあります。
しかし、複数業種の建設業許可を取得する際、もっとも注意が必要なのが「専任技術者」の取り扱いです。
本記事では、複数の建設業許可を取得する際の専任技術者のルールや注意点を、実務目線でわかりやすく解説します。
1. 基本ルール:許可業種ごとに要件を満たす必要がある
複数の業種で建設業許可を取得する場合、それぞれの業種について専任技術者の要件を満たしている必要があります。
✅ 業種ごとに対応する資格または実務経験が必要!
✅ ひとつの資格・経験だけで、他業種すべてに対応できるとは限らない!
📌 例えば、
- 「電気工事業」で第一種電気工事士の資格を持っていても、「管工事業」の専任技術者にはなれない
- 「建築工事業」と「内装仕上工事業」など、関連がある業種は同一人物で対応できるケースもある(詳細後述)
2. 同一人物が複数業種の専任技術者を兼任することは可能?
✅ 同一営業所であれば、原則として1人の専任技術者が複数業種を兼任することは可能です。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
✅ 兼任可能な条件
- それぞれの業種について要件(資格・実務経験)を満たしていること
- 同一営業所であること(複数営業所での兼任はNG)
- 専任技術者として常勤していることに変わりがないこと
📌 同一営業所内で「建築一式工事業」と「大工工事業」のように関連性の高い業種を兼任するのはよくあるケース
📌 ただし、要件の確認が甘いと申請時に不備とされることも!
3. 10年実務経験による兼任には注意!
実務経験10年以上で専任技術者になっている場合、複数業種の要件を同時に満たすには、業種ごとの経験証明が必要です。
✅ 例えば…
- 「とび・土工工事業」と「解体工事業」の両方を実務経験で申請する場合、
- それぞれの工事内容に関する経験を10年以上証明する必要がある!
📌 「ひとつの現場で複数業種を行っていた」という主張は認められにくく、経験内容を明確に分ける必要がある!
📌 証明書類(契約書・注文書・請求書など)も、それぞれの業種に対応したものを準備しなければならない!
4. 資格を持っている場合のメリットと限界
✅ 国家資格(施工管理技士など)を保有していれば、関連業種での兼任がしやすい!
例:
- 1級建築施工管理技士 → 建築工事業、内装仕上工事業、屋根工事業などに対応可能
- 1級土木施工管理技士 → 土木工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業などに対応可能
📌 「この資格がどの業種に使えるか?」は「有資格コード表」で確認可能
📌 対応外の業種に使うと、申請却下になるため注意!
5. 許可業種追加の際の注意点(更新との関係も)
✅ 業種追加の申請をする際は、追加する業種について専任技術者の要件を再確認!
✅ 同時に許可更新も行う場合は、全業種について改めて書類提出が必要なことも!
📌 専任技術者が退職予定・不在になると、許可の継続自体が危うくなるため早めの確認を!
6. まとめ|複数業種での専任技術者の取り扱いは慎重に!
✅ 業種ごとに要件(資格・経験)を満たしているか確認する!
✅ 同一人物による兼任は、同一営業所でのみ可能!
✅ 実務経験による証明は、業種別にしっかりと区分して記載・立証!
✅ 申請前に、必ず「有資格コード表」や「実務経験の例示」を確認!
✅ 不明点は行政庁または専門家に事前相談するのがベスト!
「うちの技術者で複数業種の許可が取れる?」
「実務経験でどこまで証明できるか分からない…」
そんなお悩みがある方は、ぜひライフパートナーズまでご相談ください。

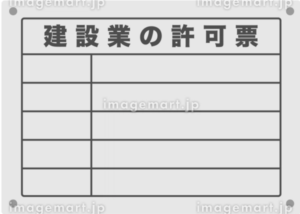




コメント